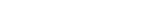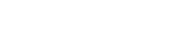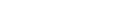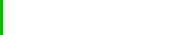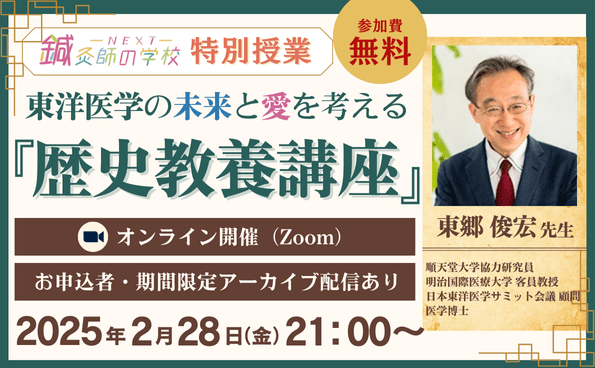DAY1
2025年3月16日(日)
21:00-22:30
ナイチンゲールに学ぶ、東洋医学と西洋医学に共通する「普遍的ケア」とは?
「白衣の天使」、「ランプの貴婦人」と呼ばれ、戦場で献身的な看護をしたと言われるナイチンゲールですが、その実際の顔は極めて実践的、合理的な思考を併せ持ち、今日のリハビリテーション医学の考えをもつ先見的な看護師でした。そして西洋医学が「実験室の医学」へと傾いていく中で、東洋医学とも通じる生命観(自然治癒力)を持ち続けた人でした。また1859年に著した『看護覚え書』は、医の東西を問わず、「患者さん中心のケア」をする上で本質的な学びを与えてくれる名著です。本講では19世紀の医学を振り返りながら、なぜナイチンゲール看護論が現代日本の医療、介護の世界で必要なのかをわかりやすく解き明かします。
DAY2
2025年4月20日(日)
21:00-22:30
統合医療の時代―現代の医療が東洋医学や相補代替医療に求めるもの
漢方や鍼灸だけでなく、アーユルヴェーダ(ヨガを含む)、アロマセラピー等の相補代替医療は90年代の欧米で現代医学を補完する新しい医療として注目されました。本講では早期から代替医療の先駆者として活躍してきたAndrew Weilの著作や90年代の米国医学界に衝撃を与えたHarvard大学のDavid Eisenbergの論文を読み解きながら、欧米における相補代替医療の再評価と今日の統合医療(Integrative medicine)へ向かうトレンド(日本を含む)について解説していきます。また同じ90年代に西洋医学も含めて医学界で中心的な考え方となったEBM(科学的証拠に基づく医療)について、「EBMの父」と呼ばれたアーチ―・コクランの戦争体験から説き起こし、その意義を解説するとともに、なぜ鍼灸分野をはじめとする相補代替医療分野の臨床研究は難しいのか、その理由についてお話ししていきます。
DAY3
2025年5月18日(日)
21:00-22:30
日本人はどのようにして西洋医学を受け入れてきたか?
徳川幕府が終焉を迎え、260年に及ぶ鎖国政策を辞めて開国した日本は、明治政府の下で西洋医学の導入を決めると同時に、それまで人々の健康を守ってきた伝統医学(漢方や鍼灸)を廃絶しようとしました。当時の医師達の反対運動もむなしく、第8回帝国議会(1889)で漢方医存続の運動は否決され、漢方は暗黒時代を迎えます。鍼灸はかろうじて存続が認められたものの、その内容は西洋医学的な解釈ですっかり読み替えられました。この点、西洋医学と同等のポジションを獲得した中国や韓国と大きく事情が異なります。ではなぜ維新期に日本ではそんなに西洋医学がすんなりと受容されたのでしょうか?本講義では世界史的な視点から大航海時代のイエズス会士の医療活動、江戸期に来日したオランダ商館医と蘭方医との交流、宝暦年間以降にさかんに行われた解剖(観臓)や種痘導入の経緯に触れつつ、当時の日本人が求めていた「新しい医学」とは何だったのかを考えていきます。
DAY4
2025年6月22日(日)
21:00-22:30
西洋医学の中で東洋医学(漢方・鍼灸)はどのように生き残ったか?
1874年、明治政府は近代的な医療制度を規定した「医制」を発布、そこでは漢方医学を廃絶し、鍼灸についても西洋医の監督下に置くことを明記しました。漢方存続運動は第8回帝国議会(1895)で頓挫しますが、鍼灸については生理学を専門とする医師や臨床家の中から、西洋医学的に治効メカニズムを明らかにしようとする者(石川日出鶴丸、石川太刀雄・橋田邦彦・杉靖三郎・板倉武)が現れました。本講義では東洋医学・鍼灸を国民の医学にしようとした、これらの医師達の「熱い想い」に触れるとともに、明治期に行われた脚気論争に見る西洋医学と東洋医学のアプローチの違いについても解説していきます。
DAY5
2025年7月20日(日)
21:00-22:30
戦争とGHQによる鍼灸禁止勧告を乗り越えてー「科学的」鍼灸の光と影
日本は1945年に敗戦。戦前、日本医学研究会を主宰し、国による伝統医学支援を企図しながら、日米開戦時に文部大臣の地位にあった橋田邦彦はA級戦犯に問われ、巣鴨刑務所に連行される直前に服薬自殺を遂げました。GHQは7年間にわたって占領下の日本の政治や経済等、様々な側面で改革を遂行しましたが、医療改革を推進したサムズ准将が鍼灸、柔道整復の禁止勧告を出すと、学界、業界団体がこぞって反対運動を展開しました。本講義ではこの「マッカーサー旋風」と呼ばれる反対運動について解説するとともに、戦後から1970年代の鍼麻酔研究までの日本における鍼灸研究の様相、鍼灸大学の設立、東洋医学の心身医学への影響などについて概観します。
DAY6
2025年8月17日(日)
21:00-22:30
日本の「古典的鍼灸」「漢方」はなぜ大正、昭和期に「復興」したのか?
19世紀の後半にはこれまでの歴史で人類を悩ませてきた感染症の原因となる細菌が多く発見され、西洋医学は大きな発展を遂げましたが、臨床面では治せない病気も多く、効果的な治療を受けられないまま死んでいく患者が後を絶ちませんでした。こうした中、「自分の身体は自分で治すしかない」と心に決めた人たちが創始した医療があります。百花繚乱と思えるほど多様な民間療法、自然療法が依拠したのは「伝統」でした。また、この時期における伝統への回帰は、大正、昭和期における精神世界の再評価と切り離しては考えられません。その様相は「スピリチュアル」なセラピーがひそかに人々の支持を得ている現代の日本とも通じる部分があります。本講義では、当時の日本の文学・哲学にも言及しながら、日本人の「健康観」に迫りつつ、鍼灸再興の祖としてその後の鍼灸界に大きな貢献を果たした沢田健、柳谷素霊の功績、および沢田流、経絡治療成立の道のりについて解説していきます。
DAY7
2025年9月21日(日)
21:00-22:30
中国の歴史と医学(1)中国医学という「物語」がもつ複数性
現代医学が過去1世紀の間、日進月歩で進歩してきたように、伝統医学も常にその時代のニーズや状況に影響をうけながら発展してきたはずです。中国では漢民族と北方の異民族による度重なる王朝の変遷に加え、印刷技術導入による情報革命の中で医学の在り方も大きく変わっていきました。したがって現代の中国医学、漢方医学、鍼灸医学について理解するためには、中国と日本それぞれの通史をおさえておくことが肝要です。本講義では古代から清代までの中国史を概観しながら各時代の宗教(道教・仏教・儒教)を含めた文化や政治の様相と医学との関係について概説していきます。特に中国医学の基本的な考え方が形成された春秋・戦国期の自然哲学や遣隋使、遣唐使を通じ、律令制度下の日本にも大きな影響を及ぼした隋唐期までの医学、仏教などを中心にわかりやすく解説していきます。
DAY8
2025年10月19日(日)
21:00-22:30
中国の歴史と医学(2)典籍の成立~宋代の「医学ルネッサンス」まで
第7講を踏まえ本講では『黄帝内経』、『傷寒論』をはじめとする中国医学の基本典籍が成立した後漢期から「医学ルネッサンス」が起こった宋代、そして運気論の影響を受けながら各々の医家が独自の理論を発展させた金元期から明代までの医学を扱います。文献でたどれるだけでも2200年近くの歴史を持つ中国医学ですが、複雑な医書の伝承の中で、多くの注釈書が編まれ、解釈も多様化していきました。これは釈迦という一人の聖人の教えを伝える仏教において多くの解釈と経典、宗派が生まれた歴史と似ています。また北宋期の情報革命(印刷技術の普及)の中で医学知識へのアクセスが飛躍的に向上したことにより、医家達が国家が決めた局方を離れ、多くの「古医書」を並列的に参照しつつ、自身の臨床に即した理論や処方を組み立てていくようになります。本講義ではそのような中国医学のダイナミックな変容の過程を一部ですがみていくことにしましょう。
DAY9
2025年11月16日(日)
21:00-22:30
日本の歴史と医学(1)―日本医学と中国医学との「距離」-コンテクストの違い
日本への大陸の医学の伝来は6世紀までさかのぼります。当初、百済を通じて伝えられた大陸の医学は、推古朝以降、遣隋使、遣唐使を介して政治制度や仏教とともに伝えられ、律令制度の下で医療もシステム化が進みます。この時期には多くの医学書が舶載されましたが、地理的な隔絶に加え、894年に遣唐使が廃止されると、他の文化と同様、医学領域においても日本化が進みました。984年に丹波康頼が円融天皇に献上した『医心方』もその編集方針を見ると実用性が重んじられ、日本独自の「文脈」で受容がなされていることが分かります。宗教面でも道教が主流だった中国と異なり、日本では中近世を通じ、仏教的な身体観がより濃厚で、このことが医学の実践においても大きな影響を与えたと考えられます。本講ではこのような文化的な側面に着目しながら日本人がどのように中国医学をassimilate(消化)していったのかをさぐります。
DAY10
2026年1月18日(日)
21:00-22:30
日本の歴史と医学(2) まとめ「こころ」を支える東洋医学の未来
今日、日本の街にはたくさんの鍼灸院の看板があり、インターネットを開けば東洋医学を標榜するおびただしい数のセラピーが目に飛び込んできます。近世の日本も同じでした。前講でお話した通り、大陸から伝わった医学は日本流にアレンジが加えられ、漢方、鍼灸それぞれに多くの流派が生まれ、これにオランダ人医師を介して伝えられた蘭方医学が加わって、日本近世の医学は百花繚乱の様相をみせます。鍼灸の分野に限って言えば、杉山和一ら盲人の鍼医らによって鍼管を用いた繊細な鍼つかい(管鍼法)が普及し、今日の日本の鍼臨床に多大な影響を遺しました。漢方分野でも複雑な理論を廃して、シンプルな理論のもとに柔軟な処方運用を志向する古方派が生まれるとともに、中国医学の徹底的な検証を目的とした考証学派とその緻密な文献研究を生み出しました。
今日の日本におけると東洋医学とは、こうした過去の複雑な「文脈」の中に成立しています。この歴史を踏まえる中であなたがセラピストとして目指す「生き方」がきっと見えてきます。